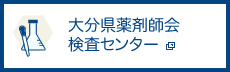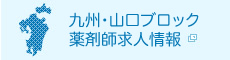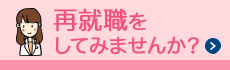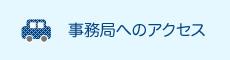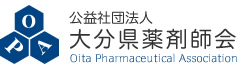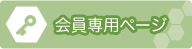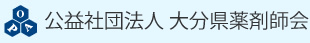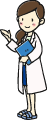薬の種類

薬には様々な色や形があり、湿布薬などの貼り薬や点眼薬など患部や用途に合わせて使いやすくしてあったり、カプセル剤や糖衣錠など飲みやすく工夫したものがあります。
そのほか錠剤、散剤(粉薬)、顆粒剤、液剤、坐薬、塗り薬、吸入剤、注射剤などがあります。
薬を飲むときは、コップ一杯の水もしくは白湯で飲むようにしましょう。
水の量が足りないと喉の粘膜に炎症を起こしたり、潰瘍ができたりすることがあります。
錠剤やカプセル剤は必ずプラスチックの包装から取り出して服用してください。また勝手にカプセル剤を開けて中の薬を出したり、錠剤をつぶすことはやめましょう。薬によっては効果がなくなる場合があります。
錠剤やカプセル剤が飲みにくい人は、医師・薬剤師に相談すると、他の剤形に変えられる場合もあります。
医療用医薬品と一般用医薬品

医療用医薬品とは医師の処方箋がなければ使用できない薬で、作用が強く患者さんそれぞれの病態に応じて処方されます。
一般用医薬品は一般薬、大衆薬ともいわれ、街の薬局・薬店で購入することができ、比較的安全性が高く、多くの方の共通した症状に対応することができるものです。
薬のかたち
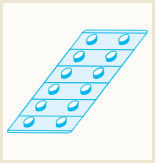
苦味を抑えたり、1日1回で効くように工夫したものもありますので、むやみにつぶして飲まないように注意しましょう。
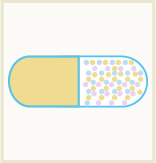
粉末状や顆粒状の薬などをカプセルの中に入れたものです。

粉末状の薬です。湿気を嫌うので保管に注意しましょう。

散剤より粒が大きく、においや苦味を抑えたり、溶けやすくするなどの加工がされたものです。

シロップ剤のように成分の一部が沈んでいるものもありますので、軽く容器を振って、1回分を量って飲みましょう。また容器に直接口をつけないように注意しましょう。
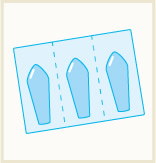
肛門や膣などに入れる薬です。薬を少し手のひらで温めてから薬を取り出し、人差し指を坐剤の底にあて、先のとがった方から肛門や膣内に深く挿入します。

貼り薬には、患部を治療するためのもの(例:湿布薬など)と、全身への作用を目的とするもの(例:狭心症治療薬など)があります。

皮膚などに塗って使います。薬が混ぜ込まれている材質(基剤)の違いにより、軟膏・クリームなどがあります。

容器の先に目が触れないように薬(目薬)を一滴、滴下した後、まばたきはせず、しばらく眼を閉じます。
2種類以上の目薬をさすときは、5分以上間隔をあけましょう。
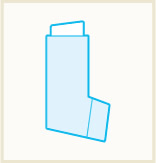
主に咳を鎮めたり痰を切ったりするときに用いられる薬です。
十分に息を吐き出した後、吸入口を口にくわえ、息を吸い込むと同時に噴霧します。
過量を吸入すると副作用を起こしやすくなりますので、指示された回数・量を必ず守りましょう。噴霧する際には容器を振って中の薬を混ぜてください。
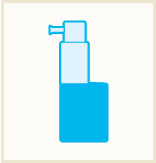
皮膚に使用するときは患部より4〜6cm離してスプレーしましょう。

直接血中や体内にはいるため、口から飲む薬に比べて効き目が速やかなのが特徴です。
また、入院中や在宅医療などでは、栄養補給を目的とした高カロリー輸液製剤などが点滴として静脈内に使用されます。
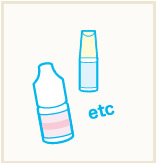
薬にはこの他にも点鼻剤、点耳剤、浣腸剤などさまざまなかたちのものがあります。
薬によってそれぞれ使い方がちがいますので、医師や薬剤師に使い方をよく聞いて正しく使いましょう。